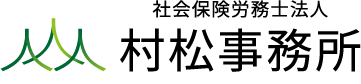SNS等に労働者の募集に関する情報を載せる際の注意点
◆労働者の募集広告には、募集主の氏名等の表示が必要
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています(第5条の4)。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案(闇バイト)が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、厚生労働省は、SNS等を通じて直接労働者を募集する際には、①募集主の氏名(または名称)、②住所、③連絡先(電話番号等)、④業務内容、⑤就業場所、⑥賃金の6情報は必ず表示するよう、事業者に呼びかけています。
○「住所(所在地)」はどこまで記載すればよいか?
ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
○「連絡先」として何を記載すればよいか?
電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問合せフォ ームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
○氏名等の情報自体を記載せず、氏名等の情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することでも問題ないか?
会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に上記6情報を記載する必要があります。
○業務内容、就業場所および賃金については、職業安定法第5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じように詳細を記載する必要があるか?
必ずしも同じである必要はないが、求職者が誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があるとしています。例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給1,500円~」とする形でも、記載があれば、直ちに職業安定法第5条の4違反とはならないと考えられるとしています。
【厚生労働省「労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」】
外国人の雇用実態に関する初の調査結果から
◆外国人雇用実態調査とは
厚生労働省は、「令和5年外国人雇用実態調査」の結果を公表しました。この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況および当該事業所の外国人労働者の状況、入職経路、前職に関する事項等について明らかにすることを目的として、初めて実施されました。
同調査は、雇用保険被保険者5人以上かつ外国人労働者を1人以上雇用している全国の事業所および当該事業所に雇用されている外国人常用労働者が対象で、抽出された9,450事業所のうち有効回答を得た3,534事業所および1万1,629人について集計しています。調査結果のポイントは以下の通りです。
◆事業所に対する調査
外国人労働者数(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人で、在留資格別にみると、「専門的・技術的分野」が35.6%、「身分に基づくもの」が30.9%、「技能実習」が22.8%となっています。
一般労働者が毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む)は26万7,700円で、1か月の総時間(所定内実労働時間)は155.8時間、超過実労働時間は19.8時間となっています。
外国人労働者を雇用する理由は、「労働力不足の解消・緩和のため」が64.8%と最も高く、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が56.8%、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が18.5%、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」が16.5%となっています。
◆労働者に対する調査
外国人労働者の国籍・地域をみると、ベトナムが 29.8%と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が 15.9%、フィリピンが 10.0%となっています。
就労上のトラブルや困ったことについては、「なし」が82.5%、「あり」が14.4%と回答しています。「あり」と回答した人の内容(複数回答)をみると、「紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった」が19.6%、「トラブルや困ったことの相談先がわからなかった」が16.0%、「事前の説明以上に高い日本語能力が求められた」が13.6%、「その他」が34.5%となっています。
今後、外国人の雇用を検討する際の参考としてください。【厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査の概況」】
障害者の雇用状況と法定雇用率引上げ
~厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」等より
厚生労働省は令和6年12月20日、令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率。民間企業においては2.5%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
◆民間企業における雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新
民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されている障害者の数は67万7,461.5人(3万5,283.5人増、対前年比5.5%増)、実雇用率2.41%(対前年比0.08ポイント上昇)で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。一方で、法定雇用率達成企業の割合は46.0%(対前年比4.1ポイント低下)となっています。
◆雇用者の内訳では、精神障害者の雇用増加の伸び率が大きい
雇用者のうち、身体障害者は36万8,949.0人(対前年比2.4%増)、知的障害者は15万7,795.5人(同4.0%増)、精神障害者は15万717.0人(同15.7%増)と、いずれも前年より増加しています。特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。
◆法定雇用率未達成企業の状況
法定雇用率の未達成企業は6万3,364社で、そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、64.1%と過半数を占めています。また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は3万6,485社であり、未達成企業に占める割合は、57.6%となっています。
法定雇用率は、令和8年度に2.7%へと段階的に引き上げられます。企業は継続して障害者雇用の推進に取り組む必要があります。【厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」】