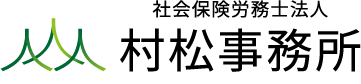2026年度高卒人材採用に関する確認ポイント
◆採用スケジュール
2026年3月新規高等学校卒業者の選考日程は、下記のとおりです。
・ハローワークによる受付開始:6月1日
・学校への求人申込みおよび学校訪問開始:7月1日
・生徒の応募書類提出開始:9月5日(沖縄県は8月30日)
・就職試験(選考開始)および内定開始:9月16日
高卒人材の募集は、ハローワークで求人受付をした上で高校への求人申込みをするなど、大学新卒者や中途採用と異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
◆応募書類に変更あり
厚生労働省の履歴書様式例から性別欄が削除されたこと等を踏まえ、全国高等学校統一応募用紙が、2026年度より見直されます。履歴書と調査書とで、それぞれ次のような変更点あり。
◆履歴書の変更点
1「性別欄」を削除
2「学歴・職歴欄」を「在籍校欄」と「職歴欄」に変更
3「趣味・特技欄」を削除
4「志望の動機欄」を「志望の動機・アピールポイント欄」に変更
「志望の動機欄」には「志望の動機、自己PR、特技等を記入すること」、また「備考欄」には資格や校内外の諸活動、志望の動機・アピールポイント等「以外で記入したい事項がある場合に記入すること」とされています。
◆調査書の変更点
1「総合的な学習の時間」を「総合的な探究(学習)の時間」に変更
2「身体状況欄」を削除
3「本人の長所・推薦事由欄」を「本人のアピールポイント・推薦事由等欄」に変更
4「特記事項欄」を追加
5 押印を削除
「特記事項欄」は、「休学の期間がある場合」「職業の特性等において必要な要件として、身体状況(視力及び聴力など)及び配慮事項の記載が求められる場合」などに記入すること、とされています。
【厚生労働省「令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました」】
従業員の不祥事発覚時の初動対応
◆初動対応の基本
従業員による不祥事が発覚した場合、企業がその対応を誤ると、社内外からの信用を大きく損ねてしまう可能性があります。被害を最小限とするために、基本的な対応策を押さえておきましょう。
①担当者を選任し、事実関係を把握
まずは事実関係を迅速に把握することが重要です。担当者を選任し、調査に当たります。関係者へのヒアリングや関連資料の確認を通じて、正確な情報を収集しましょう。その際、誰が、どのように調査を行うのかには慎重な判断が必要です。専門家に相談することも視野に入れておきましょう。社外からの問合せが想定される状況であれば、対応方針を決めておくのも重要です。
②情報開示とコミュニケーション
不祥事の事実が確認されたら、速やかに情報開示を行います。被害者、株主や取引先、従業員などに対して、誠実かつ透明性のあるコミュニケーションを図ることが信頼回復の第一歩です。確かな事実に基づき、冷静かつ真摯に対応を行います。情報開示の範囲は事案によって異なりますが、社会的影響や被害者保護、再発防止の観点から判断していきます。
③被害者対応
不祥事によって被害を受けた方々への対応も重要です。被害者の立場に立ち、誠実に謝罪し、適切な補償を行うことで、企業の責任を果たします。信頼を取り戻すためには、迅速かつ誠実な対応が不可欠です。
◆再発防止に取り組む
初動対応のあとは、原因を徹底調査し、内部統制の強化や従業員教育など、再発防止に取り組むことが重要です。従業員の不祥事など考えたくないことかもしれません。ですが、誤った対応をしないよう、準備をしておくことが大切です。
出所者を雇う協力雇用主に対する支援制度
◆協力雇用主とは?
刑務所や少年院の出所者、保護観察者などを雇用し、または雇用しようとする意思があるとして保護観察所に登録した民間事業主のことです。協力雇用主は、就労機会の提供だけでなく、社会生活の指導や助言をする役割も担います。全国で約2万5,000社が登録していますが、実際に雇用している会社は4%ほどです。
協力雇用主になるためには、保護観察所(国)に登録する必要がありますので、まずは事業所の所在地を管轄する保護観察所に連絡します。その際、協力雇用主から暴力団を排除するため、役員等名簿、登記事項証明書等の提供が求められます。
◆協力雇用主が出所者を雇うまでの流れ
①保護観察所に登録して協力雇用主になる
②ハローワークに求人をかける(制度上、保護観察所からは出所者の紹介はないため)
③ハローワークに応募した出所者を雇用する
◆協力雇用主に対する支援制度
①保護観察所による相談支援
本人への接し方や配慮すべき事項等については、保護観察所が相談に乗ってくれます。具体的には、心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官や地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けることができます。
②協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金
実際に雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し、年間最大72万円の奨励金が支払われます。
条件として、労災保険・雇用保険の加入手続を行っていることなど、一定の要件を満たす必要があります。また、協力雇用主は、就労継続のための指導等(挨拶や言葉遣いの重要性を説き、具体例を用いて人への接し方について助言を行うなど)と、指導等内容の報告が求められます。
③公共工事等の競争入札における優遇制度
地方自治体の間で公共工事等の競争入札における協力雇用主に対する優遇制度の導入が広がっており、その場合、優遇を受けられることがあります。【法務省「協力雇用主」】